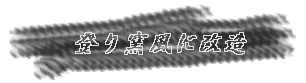初代登り窯風の窯作り
灯油窯
耐火断熱レンガ イソライト 138個 ※耐火断熱レンガは金ノコで簡単に切ることができます
鉄アングル 40㍉×40㍉の鉄アングル
断熱石綿30㍉
※内部に巻く事により断熱・燃費アップ
この窯は、登り窯風で本焼の熱を、素焼きの窯に送り込んで素焼きもします
重要:窯の中の温度は1250℃まで上昇しますので、制作に自信のある方以外はおすすめ出来ません
・・・・・窯作りの事なら何でも、ご相談ください・・・・・
現在本焼の熱風を利用して薪を焚く穴窯風・登り窯風薪窯作りしています
穴窯風・登り窯風薪窯のページ製作中
熱電対(17㍉)が値段が高いので壊さないよう窯詰・窯出の時、注意
3本目 (;_;)
さや鉢による焼締焼成の風景
さや鉢の中に、炭、藁、籾殻を入れて焼成すれば
薪窯でしか焼くことができなかった緋襷、胡麻、ビードロ、緋色、焼焦げを簡単に焼くことがてきる
ひ‐だすき【緋襷】
(火によってできた襷文タスキモンの意) 備前焼で、藁や蘆の葉を器物の肌につけて焼き、その部分の肌色が赤く明るくなり、襷形をなすもの。その自然的な変化に面白味があり、珍重される。
ごま【胡麻】薪の灰が器に降り掛かり、高温で熔けて胡麻粒をまぶしたようにみえるもの。黄色に発色する場合が多い
ビードロ【ビードロ】自然釉に含まれる鉄分が還元焼成で変化し、ガラス質の青緑色のビードロ釉となって器の表面に溜まったり、流れ下がるのが最大の魅力
やきこげ【焼焦げ】器に灰が厚く掛かると、その部分が炭素を多く含んで強い還元状態になり、肌に焦げを生じ、灰の掛かり具合で、褐色や黒褐色に変わる