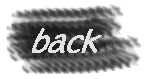素 焼 き
釉薬を掛けるのに必要な強さと適度の吸水性をもたせるのが目的
温度は普通750〜800℃くらい
別に素焼きしないで、本焼でも OK (焼締め)
釉薬も掛けないし、素地をただ焼くだけだからといって・・・・・
素焼きの窯詰めの注意点
作品が完全に乾いているかを確かめる
水分が急膨張して爆発を起こし、作品が粉々ににる
キズを調べる
キズは焼くとモット大きくなる 傷物・形の悪い物もタタキ壊して土に戻し、また形成
窯内にほぼ一杯に詰める
重ねても構いません 大きな壺や鉢の中に、小さな作品を詰めてもOK
窯に空間が多くできるときは、耐火レンガ、支柱などを入れ冷め割れを防ぐ
炎が作品に直接に当たらないよう、作品の間に耐火レンガや支柱で囲っておく
棚板をささえる支柱は、3本でも大丈夫(ガタツキがなく安定)上から下まで、1本の柱になるよう
素 焼 き の 方 法
窯の蓋を少し開けておきます
温度の急上昇は、最も危険 ・・・爆発の原因・・・
350℃以上になると、素地に含まれている有機物の燃焼、結晶水の放出
蓋の隙間から水蒸気がでる
500℃位になって、蓋を少し閉じる
これで、「あぶり」は終わりますが粘土の中の石英が573℃で変化し、急膨張しますので、窯内に温度差があると、ヒビ割れの原因
600℃がすぎて、蓋を密閉して、800℃前後までゆっくり温度を上げて素焼きの完了
バーナー部やダンパーのスキ間から冷たい空気が入らないように閉じる
素焼きの注意
900℃以上に素焼きしますと、素地がだんだんと焼締り、吸水性がなくなり、釉薬の接着が悪くなる
600℃以下で素焼きを終わりますと、素地がまだ、粘土状のままで釉薬の水分によるヒビ割れの原因
素焼きの温度は、粘土によって多少の違いがありますが、大体700〜800℃位です
素焼きにかける時間は、100℃1時間として800℃で8時間が標準です