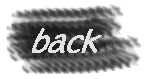釉薬つくり
松灰の釉薬をつくる
素地の表面にガラス質の皮膜をつくり、水分の浸透を防いだり、よごれがつきにくくします
釉薬の発見は、薪を燃やした灰が、土に含まれる長石や珪石と自然に溶けて混じりあい、自然釉になった事が、きっかけ
釉薬は、重量比で調合し、磁器製のボールが入ったポットミルに、釉薬の原料と適量の水を入れて、回転させ、よくすりつぶす
使用する量が少ない場合には、乳鉢ですります
非常に微妙で、変化しますので自分の好みの釉薬を作って下さい
釉薬の直し方
自作の釉薬でも、既製の釉薬でも、溶け具合や、釉調を変更したい時に、修正の材料を加え直す
熔け過ぎ・流れすぎの場合
カオリン・蛙目粘土・ろう石のいずれかを加えます
釉薬の量1㍑に対して、20㌘位を試しながら調整
熔けの不十分な場合
土灰・石灰石などアルカリ系材料を加える
釉薬の量1㍑に対して、土灰なら20㌘、石灰石なら5㌘前後
修正した時は、それを記録しておいて、後々の参考にすることをお奨めします
天然灰を使った伝統的な釉薬の調合例
| 木灰 | 長石 | 藁灰 | 釉の調子 | |
| 1 | 90% | 5% | 5% | つや消し、少しちぢれ、伊羅保調 |
| 2 | 70 | 15 | 15 | 光沢よく、透明性の結晶を起す |
| 3 | 60 | 30 | 10 | 光沢よく、透明性強い、ビードロ調 |
| 4 | 30 | 60 | 10 | 長石釉 |
| 5 | 10 | 80 | 10 | 泡多く、志野風 |
釉薬配合
| 織部釉 | 長石70 合成土灰30 酸化銅5 |
| 黄瀬戸釉 | 長石30 合成土灰70 ベンガラ3 |
| 藁灰釉 | 長石40 藁灰30 合成土灰30 |
| 鉄赤釉 | 長石50 藁灰12 合成土灰23 ベンガラ12 |
| ビードロ釉 | 長石40 天然木灰60 |